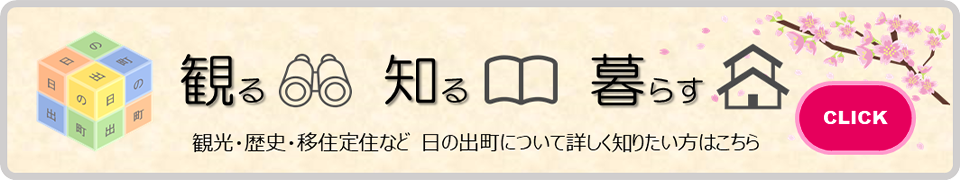しかのゆ ものがたり・まひきざわとうげのまいぞうきん
鹿の湯ものがたり(しかのゆものがたり)

鹿の湯跡

鹿の湯付近に立てられている看板
塩沢の宝光寺の裏山に「鹿の湯」と呼ばれる温(鉱)泉場の跡がある。今はおとず(訪)れる人もなく、大きな樫の木が根元も太くひっそりと立つだけである。
その昔は、けが(怪我)やひふびょう(皮膚病)によくき(効)くといわれ、評判の湯であった。
今から四〇〇年あまりも前の、宝光寺を開いた以船文済という坊さんが、この地にそうあん(草庵)をいとなんでいたころの話である。
ある日、一頭のシカがこの草庵の前を行き来していた。文済はこれを見ていぶかしく思い、気をつけてみると、そのシカはあしにひどい怪我をしており、とても痛々しそうであった。
シカはつぎの日も、つぎの日も同じように行ったり来たりした。文済はいよいよ不思議に思い、後ろをつけて、確かめてみた。すると、シカは草庵の北側の谷間へ向かい、こんこんとわき出る泉にひたり、傷ついたあしをすすいでいた。
やがて、その傷も日がたつとすっかりよくなり、シカはうれしそうにと(跳)びはねて、どこへともなく走り去っていった。
文済はこの泉を「鹿の湯」と名づけ、さっそく怪我で苦しんでいる人にためしてみたところ、みるまになお(治)ってしまったという。
このことが人から人へ伝わると、怪我や皮膚病の人たちがつぎつぎと治しに来るようになった。寺の山門の外には大きな浴室が建ち、明治のころまでたいへんはんじょう(繁盛)したという。
天正十八年、八王子城攻防戦のさいに傷ついた武士たちも、おおぜいとうじ(湯治)に来たと伝えられている。また江戸時代はたもと(旗本)溝口豊前守はここにいしどうろう(石灯籠)をきしん(寄進)している。
おわり
(注)「青木十治家文書」によると、明治元年(1868)十一月、引田村の健蔵が宝光寺から境内の湯治場を借り、湯屋を営業している。期間は明治二年から十一年までの十年であった。家賃が月に銭二十五匁、二階下は四百文、湯代は一駄につき百文ずつを納めるように取り決めている。
馬引沢峠の埋蔵金(まひきざわとうげのまいぞうきん)
むかし、雨のはげしく降る日のことであった。1台の荷車がまひきざわ(馬引沢)峠を青梅の吉野方面へと登って行った。人夫引く荷車のかたわらには、数人の侍がつき添っていた。
雨は、すでにいく日も降り続き、峠の道はひどくぬかっていた。荷車は輪をとられて大きく傾き、倒れんばかりになっては、また逆に傾く、文字どうり泥まみれの道中であった。荷は重く、侍も人夫も疲れはてていた。
実は、この荷車には金貨・銀貨がまんさい(満載)されており、侍はそのためのごえい(護衛)であった。とき(時刻)もおそく、峠の道はすでにうす暗くなっていた。またもや、荷車は大きくかしいで、そのまま動かなくなってしまった。おそらく車の軸が折れたからであろう。
これ以上、荷を積んだまま峠を越えるのは無理と判断したのだろうか。侍たちは人夫に荷をおろすように命じた。そして、どこか適当な場所にそれをかく(隠)して、ひとまず、今日のところは引きあげ、天気の回復を待ってふたたび出なおそうと相談がまとまった。
荷をおろし終わると、道から少し入ったやぶ(薮)の中に穴を掘らせ、そこに荷をひとつのこらずうず(埋)めた。雨はその間もようしゃなく降り続き、さいわい、この作業中、まったく人通りもなく、ほかに見ているものもなかった。無事処理が終わったとみるや、侍たちは秘密を守るためと、人夫をその場でき(斬)りすててしまった。
それから、侍たちは急に今埋めたばかりの荷を自分のものにしたくなり、たがいに斬り合いをはじめた。それは、あたかも雨の中のじごくえ(地獄絵)のように、むごいものであった。傷つき、死に、かろうじて一人、生きのこった侍も重い傷を負っていた。
一夜が明け、里人に助けられた侍は、故郷へと帰っていった。
そして、いく年かの時が流れた。
ただ一人、生きのこった侍は、傷をなおして人夫をともない荷車を引いて馬引沢峠へとやってきた。今日こそ、数年前に埋めた金貨・銀貨を一人じめできると、侍は心うきうきしていた。
しかし、歳月は、侍を思いのままにはさせなかった。かつてのいまわしいさつりく(殺戮)の場も、金貨・銀貨を埋めた場所さえも、草が生え、木が茂って、そこがどこであるのか、まったくわからなくなっていた。
侍は何度も何度も場所を変えて掘ってみた。しかし、なにひとつとして出てはこなかった。
そして、この馬引沢峠には、今でもそのときの埋蔵金がねむり続けているという。
おわり
お問い合わせ
東京都 日の出町 文化スポーツ課社会教育係
電話: 042-588-5794
ファクス: 042-597-6698
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
 トップページ
トップページ ホーム
ホーム 暮らし・手続き
暮らし・手続き 子育て・教育
子育て・教育 福祉・健康
福祉・健康 事業者の方へ
事業者の方へ 町のとりくみ
町のとりくみ 施設
施設